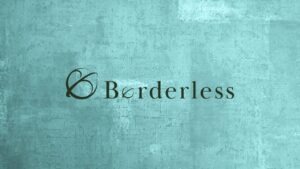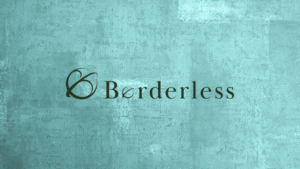[コラム] インドネシアの最新エネルギー政策から見る法務・ビジネス実務への影響 — 廃棄物発電規制と国家エネルギー政策が示す新潮流

✅ ざっくり言うと
🔋 インドネシアが2025年10月に新エネルギー規制を2本公布 — 廃棄物発電と越境電力取引が焦点
📋 大統領規則109号で廃棄物発電(WtE)が再定義され、PLNの電力買取価格が統一料金に
⚖️ 政府規則40号で越境電力取引が可能に。シンガポールへの再エネ輸出に法的根拠
🏢 日系企業にも影響大 — 投資スキーム・許認可・契約構造の見直しが必要
はじめに
今回はインドネシアにおける最新のエネルギー関連規制について説明していきます。
2025年10月、インドネシア政府は相次いで重要なエネルギー規制を公布しました。一つは廃棄物発電(Waste to Energy: WtE)に関する大統領規則109号(PR 109/2025)、もう一つは国家エネルギー政策を定める政府規則40号(GR 40/2025)です。
これらの規制は、ASEAN地域におけるエネルギー転換と脱炭素化の潮流を反映するものであり、再生可能エネルギーや循環経済に関わる日系企業にとっても見逃せない動きと考えられます。
インドネシアは日本企業の主要な投資先であり、特に再エネ・インフラ分野での投資意欲も高いことから、法務的観点からこれらの規制を整理し、実務上の留意点を考察することは有意義と考えています。
インドネシアのエネルギー政策の背景
インドネシアは人口約2.7億人を擁するASEAN最大の経済大国であり、エネルギー需要は年々増加しています。一方で、都市部における廃棄物処理問題は深刻化しており、環境汚染や公衆衛生への悪影響が指摘されてきました。
また、インドネシア政府は2060年カーボンニュートラル達成を目標として掲げており、再生可能エネルギーの導入拡大が政策的優先課題となっています。
こうした背景から、廃棄物を再生可能エネルギーとして活用する仕組みの整備と、越境電力取引による再エネの輸出促進が、今回の規制改正の主眼と思われます。
大統領規則109号 — 廃棄物発電規制の刷新
従来規制との比較
PR 109/2025は、2018年の大統領規則35号(PR 35/2018)を改正するものです。
従来規制が「機能していない」と明示的に評価されたことは注目に値します。
この表現からは、政府が過去の制度設計に問題があったと認識し、より実効性の高い枠組みを構築しようとする強い意思が感じられます。
主要なポイントと実務への影響
PR 109/2025の主なポイントは以下の通りです。
廃棄物発電の対象範囲
規制では、環境配慮型技術を用いた廃棄物のエネルギー化(PSE: Pengolahan Sampah menjadi Energi)として、以下の4類型を定義しています。
- 廃棄物発電(PSEL)
- バイオマス・バイオガス化
- 再生可能燃料化
- その他副産物化
今回の規制では主にPSEL(廃棄物の電力化)に焦点が当てられており、他の3類型については今後のエネルギー・鉱物資源省(MEMR)の実施規則で詳細が定められる予定とのことです。
この段階的アプローチは、まず実績のある電力化を優先し、その後他の手法を展開する意図と考えられます。
自治体の適格要件
PSEL事業の立地自治体には、以下の要件が課されます。
- 日量1,000トン以上の廃棄物供給能力
- 廃棄物の収集・運搬のための地方予算(APBD)の確保
- 建設・操業期間中の無償用地の提供
- 衛生サービス料金に関する地方条例の制定
これらの要件は、事業の持続可能性を担保するための前提条件と言えます。特に無償用地提供と予算確保は、自治体に相当な財政負担を求めるものであり、実務上は自治体の選定段階で慎重な検討が必要となるでしょう。
国営企業の役割とPLNの買取義務
BPI Danantara(インドネシア投資管理庁)傘下の国営企業(BUMN)が、PSEL事業者(BUPP PSEL)の選定・投資を担い、国営電力会社PT PLNがPSELで発電された電力を購入する義務を負います。
従来は競争入札が原則でしたが、PR 109/2025では、入札参加者が1社のみの場合や、環境大臣が廃棄物緊急事態を宣言した場合など、特定の状況下では直接指定も可能とされています。
この柔軟性は、迅速な事業展開を可能にする一方で、透明性や競争性の観点から懸念も残ります。
電力購入価格の統一
最も注目すべき変更点は、電力買取価格が全容量一律で1kWhあたり0.20米ドルに統一されたことです。
従来のPR 35/2018では、20MW以下は0.1335米ドル/kWh、20MW超は累進的な計算式が適用されていましたが、今回の改正で価格体系が大幅に簡素化されました。
この統一料金は、事業者にとっては収益予測が容易になる一方で、大規模事業者にとっては従来よりも不利になる可能性があります。
また、MEMRは特定の状況下で料金を見直す権限を留保しており、将来的な価格変動リスクも考慮する必要がある点、注意が必要です(意外とこうしたリスクが実際に表面化するのがインドネシアの特徴です)。
移行措置
既存のPSEL事業については、入札者指定、協力協定締結、または電力購入契約(PPA)締結が完了している場合、従来のPR 35/2018の適用が継続されます。
ただし、技術的な実現不可能性や廃棄物削減の失敗が認められた場合、当事者の合意により新規制へ移行可能とされています。
この移行措置は、既存事業者の既得権を保護しつつ、パフォーマンスが不十分な事業には新制度への移行を促す仕組みと言えます。
政府規則40号 — 国家エネルギー政策と越境電力取引
越境電力取引の法的枠組み
GR 40/2025は、2014年の政府規則79号を改正し、インドネシアの長期的エネルギー戦略を定める包括的な規制となります。
特に注目されるのは、越境電力取引に関する明確な法的根拠が初めて示された点です。
主な規定は以下の通りです。
電力輸出入の集約体制
越境電力取引は、PT PLNまたは政府が指定する事業体を通じて実施されなければなりません。
民間発電事業者が直接外国の需要家と取引することは原則として認められず、PLNまたは指定事業体に売電し、それらが輸出入を行う構造となります。
この集約体制は、国家によるエネルギー安全保障管理を重視する姿勢の表れと考えられますが、一方で民間事業者からは、市場アクセスの制限や競争阻害への懸念も指摘される可能性があるように思います。
ワンドア政策
石炭、天然ガス、バイオ燃料、電力の輸出入活動は、統合ワンストップサービス(PTSP)システムを通じて行われます。
この一元化された許認可プロセスは、手続の簡素化とコンプライアンス監視の強化を目的としていると思われます。
輸出入の基準
電力の越境輸出は、効率性と供給安全性の向上のために実施可能とされ、国内需要を優先しつつ余剰電力を輸出することで経済効果を狙うとされています。
電力輸入も同様の目的で認められ、特に国内インフラが不十分な場合、例えば国境地域への供給などが想定されています。
スワップ取引
GR 40/2025は、エネルギー資源のスワップ取引も認めています。
電力を他のエネルギー資源や商品と交換する形態も可能とされており、商業的柔軟性が認められています。
PLNの独占的地位と実務上の課題
GR 40/2025の制定により、インドネシアからシンガポールへの再生可能エネルギー輸出に法的根拠が与えられたことは大きな前進と言えます。
シンガポールは2035年までに電力の30%を域外からの低炭素電力で賄う目標を掲げており、インドネシアは重要な供給国候補と位置づけられています。
しかし、実務的には多くの課題が残されています。PLNが唯一の電力輸出アグリゲーターとして機能することで、民間発電事業者は輸出市場へのアクセスがPLNに完全に依存せざるを得ないことになります。
実際に進めるとなりますと、価格交渉力、契約条件の透明性、競争環境の確保など、今後の実施規則や実務運用で明確化すべき点は多いと考えられます。
また、GR 40/2025は高度な政策方針を示すものであり、具体的な実施細則は今後の下位規則に委ねられています(これもインドネシアの制度あるあるです)。
インフラに関わる事業ですので、いざ事業を前に進めるとなりますと大きな投資が必要になります。
このため、許認可手続、技術基準、契約ひな型など、実務レベルでの詳細が整備されるまでは、投資判断には慎重さが求められます。
日系企業への実務的示唆
これらの新規制は、インドネシアで再エネ・インフラ事業を展開する日系企業にとって、以下のような実務的影響をもたらすと考えられます。
投資スキームの見直し
廃棄物発電事業への参入を検討する企業は、自治体の適格要件やBUMNとの協業体制を前提とした投資スキームを設計する必要があります。
特に、用地の無償提供や廃棄物供給の確実性について、自治体との事前協議と法的担保が重要となります。
契約構造の精査
電力買取価格が統一されたことで、収益モデルの再構築が必要となる場合があります。
また、MEMRによる価格見直し権限や、廃棄物供給量が契約量に満たない場合の補償条項など、リスク分担の観点から契約条項を慎重に検討すべきと思われます。
越境電力ビジネスへの対応
シンガポール向け電力輸出など、越境電力ビジネスに関心を持つ企業は、PLNとの関係構築が不可欠となります。
PLNを経由した輸出スキームにおける価格設定、リスク分担、紛争解決メカニズムなど、契約交渉上の論点を事前に整理することが求められます。
許認可プロセスの理解
PTSPシステムを通じたワンドア政策が導入されたことで、許認可手続が一元化される見込みですが、実際の運用開始までには時間を要する可能性が高いです。
関連する実施規則の動向を継続的にモニタリングし、必要に応じて現地専門家のサポートを得ることが重要と考えられます。
まとめ
インドネシアの2025年10月に公布された大統領規則109号と政府規則40号は、同国のエネルギー政策における重要な転換点を示すものと言えます。
廃棄物発電規制の刷新は、環境問題と再エネ導入を同時に推進する実務的な枠組みを提供し、越境電力取引の法制化は、ASEAN域内のエネルギー統合に向けた一歩と評価できます。
一方で、PLNの独占的地位、価格決定メカニズムの不透明性、実施規則の未整備など、実務上のハードルも少なくありません。
日系企業がこれらの新規制を活用してビジネス機会を追求するには、法務・財務・技術の各側面から綿密なデューデリジェンスと、現地当局・パートナーとの緊密なコミュニケーションが不可欠と思われます。
今後も、インドネシアのエネルギー規制の動向には最新情報を押さえていく必要がありそうです。